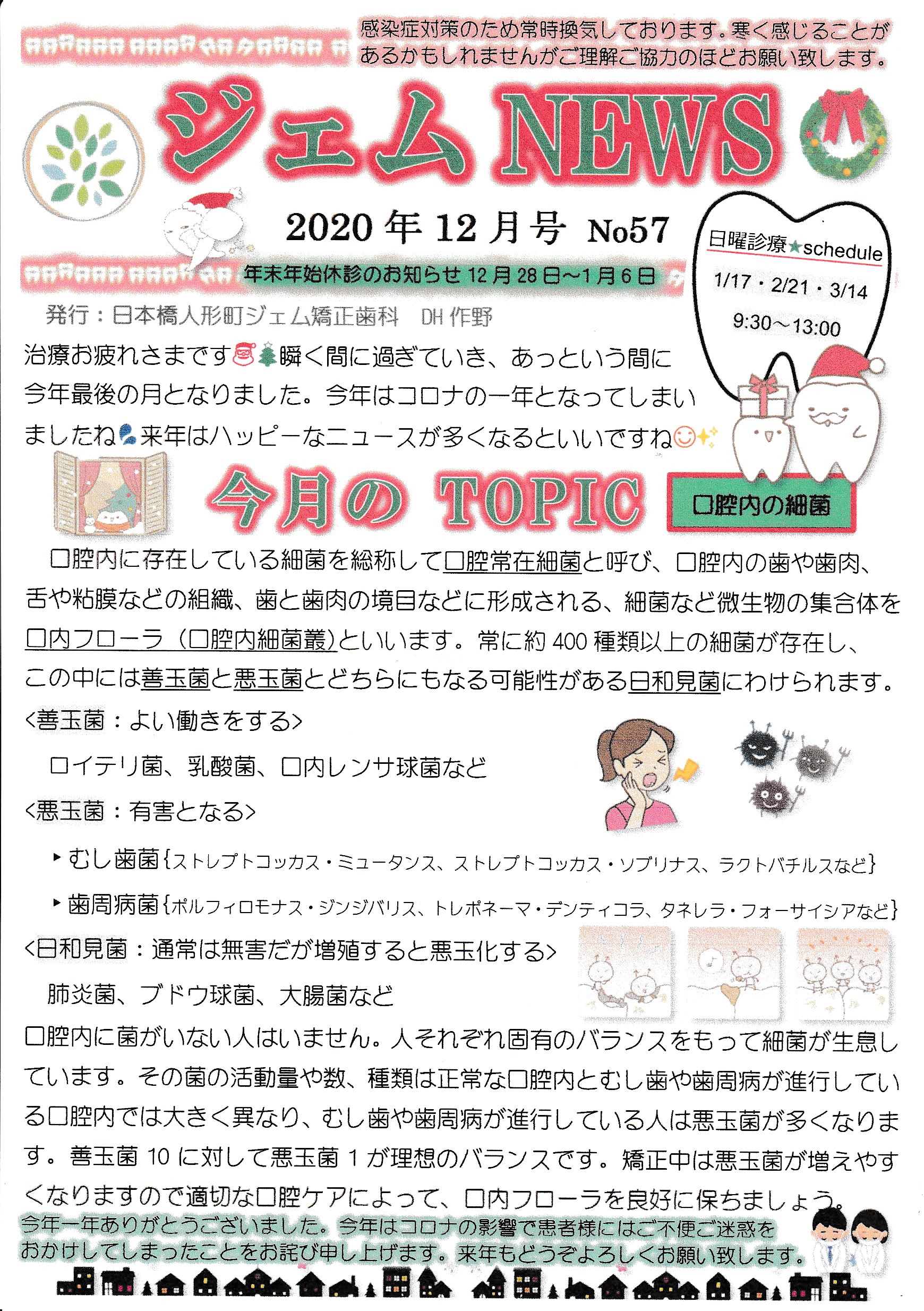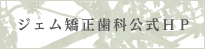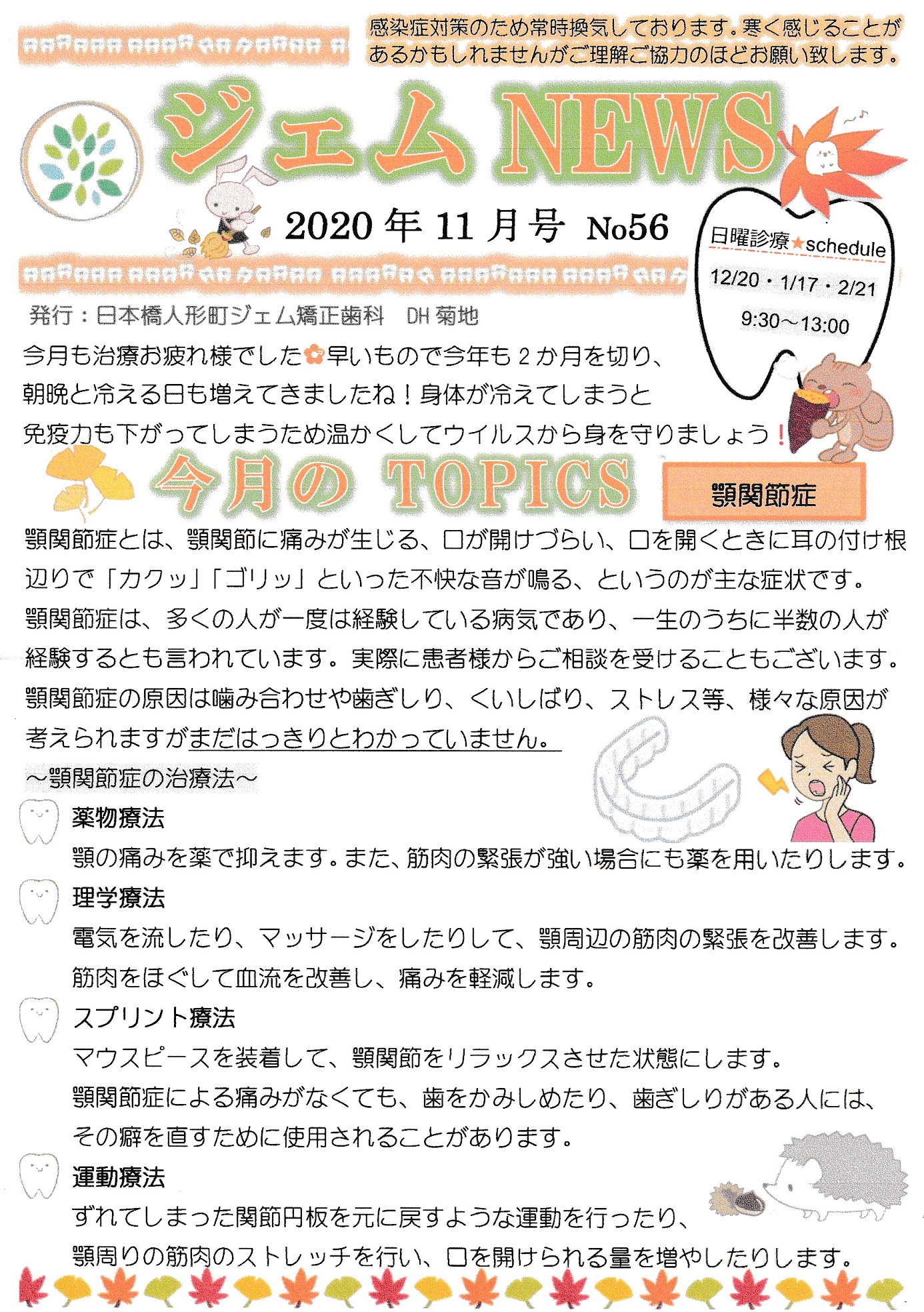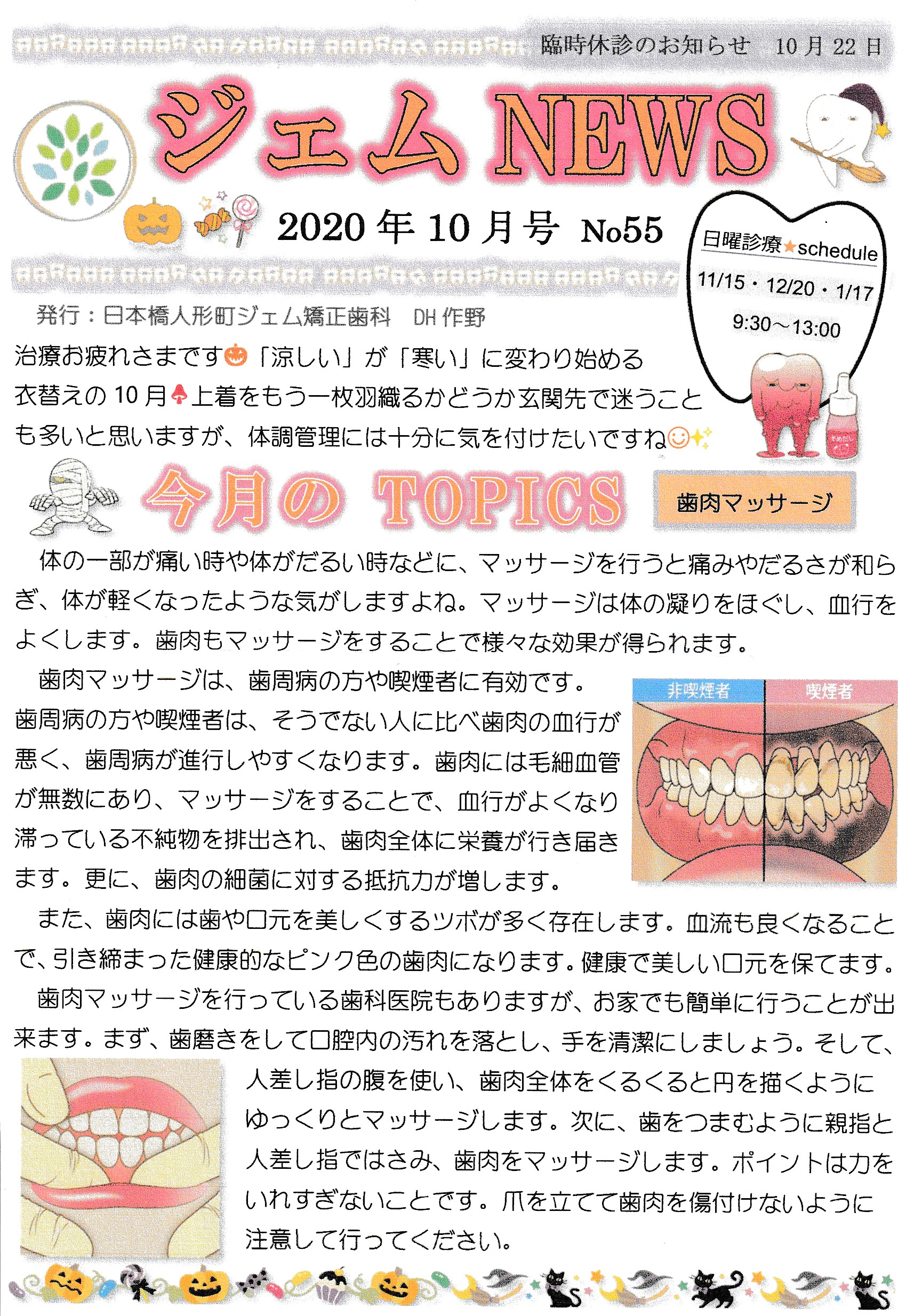ジェムNEWS 2020年12月号
ジェムNEWS 2020年12月号 №57
発行:日本橋人形町ジェム矯正歯科 DH作野
治療お疲れさまです🎅🎄瞬く間に過ぎていき、
あっという間に今年最後の月となりました。
今年はコロナの一年となってしまいましたね💦
来年はハッピーなニュースが多くなるといいですね😊✨
今月のTOPIC~口腔内の細菌~
口腔内に存在している細菌を総称して口腔常在細菌と呼び、口腔内の歯や歯肉、
舌や粘膜などの組織、歯と歯肉の境目などに形成される、細菌など微生物の集合体を
口内フローラ(口腔内細菌叢)といいます。常に約400種類以上の細菌が存在し、
この中には善玉菌と悪玉菌とどちらにもなる可能性がある日和見菌にわけられます。
<善玉菌:よい働きをする>
ロイテリ菌、乳酸菌、口内レンサ球菌など
<悪玉菌:有害となる>
▸むし歯菌{ストレプトコッカス・ミュータンス、ストレプトコッカス・ソブリナス、ラクトバチルスなど}
▸歯周病菌{ポルフィロモナス・ジンジバリス、トレポネーマ・デンティコラ、タネレラ・フォーサイシアなど}
<日和見菌:通常は無害だが増殖すると悪玉化する>
肺炎菌、ブドウ球菌、大腸菌など
口腔内に菌がいない人はいません。人それぞれ固有のバランスをもって細菌が生息しています。その菌の活動量や数、種類は正常な口腔内とむし歯や歯周病が進行している口腔内では大きく異なり、むし歯や歯周病が進行している人は悪玉菌が多くなります。善玉菌10に対して悪玉菌1が理想のバランスです。矯正中は悪玉菌が増えやすくなりますので適切な口腔ケアによって、口内フローラを良好に保ちましょう。
‐日曜診療のご案内‐
1月17日・2月21日・3月14日
9:30~13:00
‐冬期休診のお知らせ‐
12月28日~1月6日